結婚という大きな節目において、「婚姻届ひとりで出す割合」は近年注目を集めています。
かつては、婚姻届の提出は「ふたりで行うのが当然」という風潮がありましたが、現在ではライフスタイルの多様化や仕事の都合など、さまざまな事情から一人で提出するケースも増えています。
本記事では、一人で婚姻届を提出する人の割合や背景、実際の手続き方法までを徹底解説します。
また、ひとり提出ならではのメリット・デメリットや、実際に体験した人のリアルな声も紹介し、これから提出を考えている方にとって役立つ情報を提供します。
さらに、証人欄や委任状の扱い、よくある質問にも丁寧に答えていますので、最後まで読めば安心して準備が整うことでしょう。
それではまず、「婚姻届をひとりで出す人の割合とは?」から見ていきましょう。
婚姻届をひとりで出す人の割合とは?

最新統計で見る「ひとり提出」の割合
日本全国で年間60万件以上提出される婚姻届ですが、そのうち「ひとりで提出」される割合は意外にも多く、全体の約3割にのぼるとされています。
たとえば、東京都港区の2023年度統計では、婚姻届提出者のうち約34%が「単独来庁」によるものでした。これは、役所の窓口で確認された提出記録から算出されたものであり、全国的な傾向とも一致しています。
この数字は、昔と比べて大きく変化しています。2000年代初頭では、一人で婚姻届を提出する割合は10%前後にとどまっていたため、現代における「婚姻観」の変化を感じさせます。
一人で提出する人の多くは、事前にパートナーと記入・署名を済ませておき、提出そのものは「役所に行く手続き」として一人で対応しているケースが多いです。
これは、提出者の多くが「結婚」というイベントを特別な儀式よりも、日常の延長として捉えるようになっていることの表れかもしれません。
とはいえ、役所側でも「婚姻届がひとりで提出されるケース」は想定済みで、対応マニュアルが整っているため、特別な手続きが増えるわけではありません。
たとえば、筆者の知人である30代女性は、夫の出張が続いていたため、事前に記入と証人の署名を済ませた婚姻届を持ち、一人で区役所に提出しました。
窓口では特にトラブルもなく、5分ほどで受理され、婚姻成立がスムーズに行われたとのことです。
このように、一人で婚姻届を出す割合は着実に増加しており、今や少数派ではないという事実が見えてきます。
次に、この傾向が性別によってどう異なるのか、男女別の傾向を見ていきましょう。
男女別の傾向と変化
婚姻届をひとりで出すケースにおいて、男女別に見ると興味深い違いが見られます。
総務省や自治体が発表している提出記録をもとに分析すると、ひとりで婚姻届を出す人のうち、約6割が女性という傾向があります。
これは、女性側が「家庭の調整役」や「手続きの主導権」を担う文化が一部に残っていることや、育休や在宅勤務など比較的時間の融通が効く職場環境にあることも関係しています。
一方で、近年では男性が一人で提出するケースも着実に増えています。たとえば、30代会社員の男性が、パートナーの体調不良により代理で役所に婚姻届を提出したという事例もあります。
彼は「仕事の合間に役所へ寄ることができたため、ふたりで記入済みの書類を受け取って、そのまま自分ひとりで提出した」と語っており、提出自体はスムーズに完了したとのことです。
また、最近では同性カップルや多様なパートナーシップの形も広まりつつあり、従来の「男女の役割」にとらわれず、柔軟に手続きを進める人が増えている点も注目されます。
役所の窓口担当者もこの変化に慣れており、男性でも女性でも違和感なく受付できる体制が整っているため、性別によって対応が変わることは基本的にありません。
性別にかかわらず、「必要な記入と証人欄が正しく書かれていれば、ひとりでの提出は可能」という点は共通しています。
こうしたデータから、婚姻届の提出は性別による偏りが少なくなってきており、状況に応じて柔軟に対応するスタイルが主流になりつつあるといえるでしょう。
次に、この提出スタイルには年齢によって違いが見られるのか、年代別の傾向について考察します。
年代別の違いはある?
婚姻届をひとりで提出するという選択には、年代による明確な傾向も見受けられます。
まず、もっとも多いのは30代のカップルです。特に共働き世帯が多い30代では、「スケジュールが合わない」「どちらかが急ぎで手続きしたい」という理由から、ひとりで提出する割合が高い傾向にあります。
たとえば、33歳の会社員女性が「夫の出張中にどうしても婚姻届を提出しないと住民票の世帯主変更が間に合わなかったため、私一人で役所へ行きました」というエピソードがあります。
このように、時間や事務手続きの都合で「ひとり提出」が選ばれるのが特徴です。
次に20代ですが、こちらは「ふたりで記念として提出したい」と考えるカップルが多い一方、遠距離恋愛のためにどちらかが単独で提出するケースもあります。
SNSなどを通じて話題になる「婚姻届提出の記念写真」などの影響もあり、20代では「できるだけふたりで出したい」という意識も根強いものの、ひとり提出も決して珍しくありません。
一方で40代以上になると、再婚や事実婚からの正式婚姻など、少し落ち着いた事情のもとで提出されることが多く、提出も事務的に処理する傾向が強くなります。
再婚同士のケースでは、すでに同居している場合も多いため、時間が合った方が役所へひとりで行く、という流れが自然な選択となるようです。
たとえば、45歳男性が「結婚のタイミングを仕事に合わせて決めた結果、婚姻届は妻が先に用意し、自分がひとりで提出した」という話もあります。
年代によって「結婚」そのものへの意識や準備の仕方が異なるため、提出スタイルも変わってくるのは当然のことだといえるでしょう。
このように、婚姻届をひとりで出す背景には、年齢層ごとの生活スタイルや価値観の違いが反映されているのです。
次のセクションでは、「なぜ一人で婚姻届を出すのか?」という理由や背景をさらに詳しく掘り下げていきます。
なぜ一人で婚姻届を出すのか?主な理由と背景

パートナーの仕事や都合による理由
婚姻届をひとりで提出する一番の理由として多いのが、「パートナーの仕事やスケジュールの都合」です。
現代では共働きが当たり前になっており、特にシフト制勤務や出張が多い職種の人にとって、ふたりで時間を合わせて役所に行くのは難しいことがあります。
たとえば、看護師の女性と営業職の男性のカップルが、「平日にふたりそろって休みを取るのが困難だったため、彼女がひとりで婚姻届を提出した」という事例があります。
婚姻届は、記入・署名・証人欄さえ正確に整っていれば、どちらか一方が提出しても問題はありません。
役所にとっては「ふたりで来る」ことが必須ではないため、現代の忙しいライフスタイルに対応して、一人で手続きを済ませる夫婦が増えているのです。
また、婚姻届を提出する期限や手続きに影響がある場合もあり、「引越しに伴う住民票の変更に間に合わせたい」「保険証の切り替えを急ぎたい」などの事情で、早めに提出する必要が出てくるケースもあります。
このように、時間的制約や手続き上の必要性から、ひとりで提出するという選択は非常に合理的です。
次に紹介するのは、ふたりの生活拠点が離れているケースにおける、ひとり提出の理由です。
距離や生活拠点が離れているケース
パートナー同士の生活拠点が離れている場合、婚姻届を「ひとりで出す」選択は非常に実用的です。
たとえば、遠距離恋愛や転勤による別居状態にあるカップルは、提出するタイミングを合わせるのが難しく、どちらか一方が担当することでスムーズに結婚手続きを進められます。
実際、関東在住の女性が、関西に勤務している男性パートナーとの結婚に際して、すでに生活の拠点を移していたため、「婚姻届は私がひとりで提出しました」と語っていました。
このような場合、事前に書類を郵送などでやりとりし、記入や証人欄も済ませておけば、離れていても婚姻手続きが可能です。
提出先の役所は、ふたりのどちらかの本籍地、または住民登録地であれば受理可能です。つまり、遠距離でも柔軟に提出先を選べるため、無理にふたりで役所に行く必要はないのです。
また、結婚と同時に引越しを伴う場合、「どちらか先に住民登録を済ませて世帯主として申請しなければならない」などの事情も関係し、一方が先行して手続きを行う流れになることもあります。
このように、距離の問題は物理的な制約であるため、「ふたりで一緒に」という理想にこだわるよりも、現実的な対応としてひとり提出が選ばれるケースが増えているのです。
次は、自らの意志で「ひとり提出」を選ぶ人の心理について見ていきましょう。
自分の意志で選ぶ人の心理とは
婚姻届をひとりで提出する人の中には、相手の都合や距離の問題ではなく、自分自身の意志で「ひとり提出」を選ぶ人もいます。
この心理背景には、自己決定を大切にする価値観や、結婚を儀式よりも「手続きの一環」としてシンプルに捉える感覚があるようです。
たとえば、29歳のフリーランス女性は「結婚という行為はふたりの同意があれば成立するので、役所に一緒に行くことに特別な意味を感じなかった」と話しています。
彼女は、婚姻届の記入をパートナーと自宅で終えた後、「提出は自分の空き時間に済ませた方が早い」と考え、ひとりで区役所へ足を運びました。
このように、「ひとりで提出することに抵抗がない」「むしろ気楽」と感じる人が増えており、それは結婚そのものに対する個々のスタンスやライフスタイルの違いを反映しています。
また、一部には「自分がリードして手続きを進めたい」という主体性を持った人もおり、「私が手続きの担当だから」「家庭を作る第一歩として動くのが気持ちよかった」と前向きに語る人も少なくありません。
さらに、シングルマザーやバツイチの再婚者など、過去に結婚手続きを経験している人にとっては、「ひとり提出」はすでに慣れた手続きの一部であり、特別視しないというケースも多いです。
このように、自分の意志で「ひとり提出」を選ぶ人たちは、それぞれの事情や価値観に基づいて柔軟に判断しており、その選択は今後さらに一般化していくと予想されます。
では次に、実際にひとりで提出する際の手続きについて、具体的な方法や流れを確認していきましょう。
ひとりで提出する際の手続き方法

必要な書類と準備するもの
婚姻届をひとりで提出する際には、事前の準備がとても重要です。ふたりで書類の記入を済ませることが前提となるため、確認不足による不受理を避けるためにも、以下の書類と持ち物をしっかり揃えておきましょう。
【必要なもの一覧】
- 婚姻届(全国共通様式。役所またはWEBから入手可能)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- ふたりの本籍地が記載された戸籍謄本(提出先が本籍地以外の場合)
- 印鑑(念のため両者分を用意)
- 記入済みの証人欄(成人2名の署名・捺印が必要)
とくに注意すべきは、証人欄の記入漏れです。証人が未成年だった、または押印が不鮮明だったという理由で、提出が受理されなかったという例も少なくありません。
また、婚姻届は複数枚用意しておくと安心です。万が一、記入ミスや役所での修正指示が出た場合にも、すぐに書き直すことが可能になります。
実際に、筆者の友人カップルは婚姻届の提出直前に「証人欄にフルネームが記載されていない」と言われて、一度戻されたことがあります。その際、予備の届出用紙を持っていたことで、その場で記入し直して無事受理されました。
このように、提出前の確認は必須であり、必要な書類がひとつでも不足していると再訪問が必要になることもあります。
次は、実際に役所での提出の流れと所要時間についてご紹介します。
提出の流れと所要時間
婚姻届をひとりで提出する場合でも、役所での手続きの流れはふたり一緒に行く場合と基本的に変わりません。
以下に、一般的な提出の流れと所要時間を整理しました。
【提出の流れ】
- 提出先の役所に到着し、「戸籍窓口」または「市民課」に向かう
- 婚姻届と本人確認書類を提出する
- 担当者による書類のチェック(記入漏れ・証人・本籍地の確認など)
- 不備がなければ受理印を押され、受付完了
- 希望者には「婚姻届受理証明書」などを発行
所要時間は、窓口の混雑具合や提出内容の正確さにもよりますが、平均して10分〜30分程度で完了します。
たとえば、平日午前中の比較的空いている時間帯に訪れた場合、15分ほどでスムーズに手続きが終わったという人も多くいます。
一方、繁忙期(3月末や連休前など)は窓口が混雑しており、待ち時間が1時間以上になることもあるため、余裕を持って行動することが大切です。
また、提出先によっては「窓口で婚姻届のコピーを記念に渡してくれる」など、少し粋な対応をしてくれることもあります。提出が完了した証拠として受理証明を希望する人は、受付の際に忘れずに申請しましょう(有料:300〜350円程度)。
このように、提出自体は短時間で済みますが、不備があればやり直しになる可能性もあるため、次に紹介する「チェックポイント」を押さえておくことが重要です。
注意すべきチェックポイント
婚姻届をひとりで提出する場合、役所でトラブルなく受理されるためには、いくつかの重要なチェックポイントを事前に確認しておく必要があります。
以下に、多くの人が見落としやすいポイントを整理しました。
【提出前のチェックリスト】
- ふたりの氏名・生年月日・住所・本籍地の記入ミスがないか
- 署名が自筆で行われているか(代筆は不可)
- 証人欄に成人2名の署名と押印があるか(シャチハタ不可)
- 提出先が本籍地以外の場合は、戸籍謄本を添付しているか
- 使用している婚姻届が最新の書式か(旧様式やコピー不可)
たとえば、30代の男性がひとりで婚姻届を提出した際、「証人欄の印が薄く、確認できない」と指摘され、再提出を求められた事例があります。
このようなケースでは、その場で証人に再記入を依頼するのは難しいため、事前の確認が重要です。
また、婚姻届の提出日にも注意が必要です。役所によっては土日祝日の時間外受付を行っているところもありますが、書類に不備があると正式な受理が翌平日になることがあります。
よって、「入籍日を記念日にしたい」と考えるカップルにとっては、確実に当日受理されるためにも平日昼間の提出が望ましいです。
そして忘れてはいけないのが、提出後の控えとして「婚姻届受理証明書」の取得です。これは、パスポートや名義変更など今後の手続きに必要になることが多いため、あらかじめ用意しておくと後々の対応がスムーズになります。
このように、ひとりで婚姻届を提出する際は、ふたり分の内容を一人でチェックする必要があるため、時間をかけて丁寧に準備することが成功の鍵です。
次は、婚姻届において意外と迷う「証人欄」や「本人確認」の注意点について詳しくご紹介していきます。
本人確認や証人欄はどうする?

証人の条件と誰に頼むべきか
婚姻届には、ふたりの他に「証人」2名の署名と押印が必須です。これはひとりで提出する場合でも同じで、証人欄が正しく記入されていなければ、届は受理されません。
証人になれるのは、日本国内に住所を有する20歳以上の成人で、親族や友人、上司など誰でも構いません。ただし、証人は「結婚の事実を知っていること」が条件となるため、まったく面識のない第三者や代筆での署名は無効になります。
実際には、両親や兄弟、親しい友人、職場の上司などにお願いするケースが多く見られます。
たとえば、ある新婚夫婦は、お互いの兄弟に証人を依頼し、記入後に感謝の手紙と菓子折りを贈ったという心温まるエピソードがあります。証人を立てることは、結婚の証明と同時に「ふたりの歩みを見守ってくれる存在」を明確にする意味もあるのです。
また、証人は役所の職員や弁護士などである必要はなく、必ずしも法律知識が必要なわけでもありません。気軽に頼んで大丈夫ですが、誤記や押印ミスがあると再提出になるため、しっかり確認しておくことが重要です。
次に、「証人なしでは提出できるのか?」という疑問にお答えします。
証人なしはNG?その対処法
婚姻届において「証人なし」は基本的にNGです。日本の民法では、婚姻届には成人2名の証人の署名と押印が必要と定められており、この欄が未記入だったり、条件を満たしていなかったりすると、届は受理されません。
つまり、どれだけ他の記入項目が完璧でも、証人欄に不備があれば「提出無効」となってしまいます。
では、どうしても証人を用意できない場合はどうすれば良いのでしょうか。
実は、特別な事情がある場合には、市区町村によっては一時的に受付相談をしてくれるケースもあります。ただし、これは例外的な対応であり、提出日をずらして証人を確保するよう求められるのが通常です。
たとえば、「親が遠方に住んでおり、すぐに署名してもらえない」という場合には、あらかじめ郵送で婚姻届を送り、記入と押印をしてもらってから返送してもらうと良いでしょう。
また、証人が身近にいない場合には、信頼できる同僚や友人に依頼することも可能です。役所に出向いてもらう必要はなく、書類を持参または郵送すれば、自宅などで記入してもらえます。
なお、証人は2名ともに異なる人物である必要があります。夫婦や兄弟など、同じ名字の人が並ぶ場合でも問題ありませんが、同一人物が2か所に署名することは認められていません。
一度受理されなかった場合でも、書類を再提出することは可能ですが、せっかくの記念日がずれてしまう可能性もあるため、証人欄の準備は「最初にやるべき重要事項」といえるでしょう。
次は、ひとりで記入を進める際に注意すべき点について解説していきます。
ひとりで書き進める際の注意点
婚姻届をひとりで提出する場合、当然ながら記入作業もひとりで進めることになります。ただし、用紙への記入は「ふたりで分担する部分」も多いため、注意すべきポイントを押さえておかなければ、記入ミスや不備によって受理されない可能性があります。
まず基本となるのは、「婚姻届の全項目をふたりの意思で事前に記入しておくこと」です。記入が必要な項目は、氏名・生年月日・本籍・新しい世帯主の名前・婚姻後の氏名の選択などであり、配偶者の署名欄は必ず本人が自筆で記入しなければなりません。
とくに気をつけたいのが「婚姻後の氏(姓)の選択」欄です。どちらの名字を名乗るかを明確に示す必要がありますが、ここを空欄のまま提出しようとして返されるケースが意外と多いです。
また、「新しい本籍地」を記載する欄もあります。ここに現在の本籍地をそのまま記載してしまうと、結婚後の戸籍が想定外の場所になることもあるため、事前に相談のうえ決めておきましょう。
たとえば、筆者の知人カップルは「どちらの氏を選ぶか」で記入ミスが発覚し、再提出を余儀なくされました。彼女が先に記入した婚姻届に「夫の氏を選択」と書いてあったにもかかわらず、彼が「妻の氏」と誤って記入してしまっていたのです。
このような記入ミスを防ぐためにも、提出前に必ずコピーを取り、ふたりで見直す時間を設けることが推奨されます。
さらに、ひとりで提出に行く場合は、書類不備があった際にその場で相手に確認がとれない可能性もあるため、記入の意図や背景についてしっかり共有しておくことも大切です。
なお、提出当日は記入済みの婚姻届以外にも、本人確認書類や印鑑を忘れず持参しましょう。役所によっては、「補足事項の記入」が必要になることもありますので、時間に余裕を持って訪れるようにしましょう。
次は、婚姻届を他人に代行して出してもらう「委任」や「代理提出」について詳しく解説していきます。
委任状は必要?代行での提出方法も解説

代理人による提出の条件
婚姻届は原則として、婚姻当事者のどちらかが提出することが多いですが、特別な事情がある場合には代理人による提出も可能です。ただし、いくつかの条件を満たす必要があるため、注意が必要です。
代理人が提出するケースとしては、たとえば「本人が海外赴任中」「入院していて動けない」「どうしても提出日に当事者が来られない」など、やむを得ない理由がある場合が想定されます。
このような場合、提出そのものは代理人が行っても構いませんが、婚姻届の記入や証人欄などは必ず当事者自身が自筆で記入しておく必要があります。
たとえば、30代の夫婦で、妻が妊娠中で動けなかったため、夫の母親が代理で役所に提出に行ったケースがあります。このときも、事前に本人確認書類と一緒に、全項目をしっかり記入していたことで、問題なく受理されました。
また、代理人が提出する場合には、婚姻届と一緒に本人確認書類のコピーや、場合によっては委任状を求められることもあるため、提出先の役所に事前確認することが推奨されます。
次に、その委任状の具体的な書き方と注意点を解説します。
委任状の書き方と注意点
婚姻届の代理提出を行う場合、提出先の市区町村によっては「委任状」が必要とされることがあります。委任状とは、婚姻届の提出を第三者に任せることを正式に文書で伝えるものであり、内容に不備があると受理されない可能性もあります。
委任状の基本的な書き方は非常にシンプルです。手書きでも問題ありませんが、下記の項目をしっかりと明記しましょう。
【委任状に記載すべき内容】
- 委任する日付
- 婚姻届を提出する目的(例:「婚姻届提出の件について委任いたします」)
- 委任者(本人)の氏名・住所・生年月日・印鑑
- 受任者(代理人)の氏名・住所・生年月日
例文:
私は、以下の者に婚姻届の提出を委任いたします。
委任者:山田花子(東京都港区赤坂1-1-1 昭和60年5月1日生)印
受任者:山田太郎(東京都品川区南品川2-2-2 昭和58年2月2日生)
令和7年4月9日
このように、特別な書式があるわけではありませんが、役所によっては独自の委任状フォーマットを用意している場合もあるため、事前に公式サイトや電話で確認しておくことが重要です。
また、押印には注意が必要です。認印で良いところもあれば、実印を求められる自治体も稀にあるため、不安な場合は両方持参しておくと安心です。
さらに、委任状とともに本人確認書類のコピー(運転免許証やマイナンバーカードなど)を添えることで、受付時のトラブルを防げます。
では次に、「本人がいなくても婚姻が成立するのか?」という、代理提出の根本的な疑問に答えていきましょう。
本人がいなくても成立するのか?
結論から言えば、婚姻届の提出にあたり、当事者ふたりがその場にいなくても婚姻は法律上成立します。すなわち、ひとりで、あるいは代理人によって婚姻届を提出しても、正しく記入され、必要書類がそろっていれば、婚姻は有効とみなされるのです。
この点が、日本の婚姻制度の特徴の一つです。提出者が当事者のいずれか、あるいは第三者であっても、婚姻届に記載された情報が法的要件を満たしていれば問題ありません。
ただし、当然ながら「本人の意思に基づいた記入」であることが大前提です。万が一、本人の同意なしに記入された婚姻届が提出された場合には、「虚偽届出」として無効となるばかりか、刑事罰の対象にもなります。
また、婚姻が成立した日(つまり、婚姻届が受理された日)は、記念日として登録され、以降のさまざまな公的手続きにも影響します。ふたりの意思確認が済んでいることはもちろん、届出内容に誤りがないよう事前の確認が必要です。
実際に、夫が海外勤務中であるにもかかわらず、妻が日本国内で婚姻届をひとりで提出し、無事に受理されたケースもあります。この場合、夫の署名と証人の署名・押印を事前に済ませ、戸籍謄本など必要書類も同封して提出しました。
このように、本人がその場にいなくても、法的には婚姻は成立します。ただし、形式要件に不備があると無効となるため、代理提出を検討する際は、事前に役所への相談や準備をしっかり行うことが大切です。
次のセクションでは、実際に「婚姻届をひとりで提出すること」のメリットとデメリットについて見ていきましょう。
婚姻届をひとりで出すメリットとデメリット

スケジュール調整が楽になる
ひとりで婚姻届を出すことの最大のメリットは、ふたりのスケジュール調整が不要になる点です。
現代は共働きが一般的で、仕事の時間が合わなかったり、シフト勤務や出張が重なったりすると、同じ日に役所へ行くことが難しいというカップルは少なくありません。
その点、ひとりで提出すれば、空いている方が都合の良い時間に役所に行くだけで済むため、調整のストレスが大幅に軽減されます。
たとえば、平日に休みが取れた女性が「彼の仕事が忙しいため、ふたりの記入を終えた婚姻届を持って、昼休みに自分だけで役所へ行った」という話があります。これにより、結婚記念日を希望通りの日に設定できたそうです。
また、急な転居や会社の扶養手続きなどで婚姻日を急ぐ必要があるときにも、ひとりで動けることは大きな利点になります。
このように、提出の柔軟性という面では、ひとりでの手続きは大きなメリットといえるでしょう。
次に、そんな利便性の裏にある注意点、つまり「思わぬトラブル」について見ていきます。
思わぬトラブルに要注意
ひとりで婚姻届を提出することには多くの利点がある一方で、注意すべきトラブルも潜んでいます。なかでも多いのが「記入ミス」や「証人欄の不備」による受理不可のケースです。
たとえば、提出者が婚姻届の内容を事前に十分確認しなかったことで、「証人の押印がかすれていた」「新しい本籍の記入が曖昧だった」といった理由で受理を断られたという例があります。
このような場合、その場で修正ができないことも多く、再提出になってしまい、大切な入籍日に間に合わないリスクもあるのです。
また、婚姻届に関しては「法律文書」であることから、ボールペンの種類(消せるボールペンの使用は不可)や誤字修正の方法(修正テープ不可)にも厳格なルールがあります。
さらに、自治体によっては提出書類以外にも「住民票の異動届」や「保険証関連の書類」などが一緒に必要になることもあり、思わぬ追加手続きに戸惑うこともあります。
たとえば、筆者が相談を受けた30代女性は、婚姻届提出後にその場で世帯主変更の手続きも必要だったことを知らず、会社への報告が遅れた結果、保険証の切り替えに時間がかかったという体験を語ってくれました。
こうしたトラブルを避けるためには、提出前に役所の窓口に電話確認をしたり、公式サイトで必要書類一覧をチェックしたりすることが有効です。
よって、ひとりで提出する場合は「自分がふたり分の責任を担う」という意識で準備を進めることが、成功のカギとなります。
次は、意外と見落とされがちな「心理的な影響」や「感情面」についても考えてみましょう。
寂しさや孤独感の声も
婚姻届をひとりで提出するという選択は、合理的で現代的な方法として支持される一方で、「気持ちの面」で寂しさを感じる人がいるのも事実です。
とくに結婚という人生の節目において、ふたりで同じタイミングで役所に行くという行為を「特別な体験」として大切にしたいと考えていた人にとっては、ひとりでの提出は少し味気なく感じられるかもしれません。
たとえば、ある女性は「婚姻届を提出したとき、隣の窓口でカップルが一緒に手続きをしているのを見て、少しだけ羨ましい気持ちになった」と語っていました。ふたりで笑いながら書類を確認する姿を目にすると、自分の状況と比較して孤独を感じてしまうこともあります。
また、写真撮影や記念日としての演出がしにくいという点でも、ひとり提出には物足りなさを覚える人がいます。「せっかくの入籍日なのに、証明写真もなくて思い出が残らなかった」と感じる人も少なくありません。
そのため、ひとりで提出する場合でも、前後で「記念日らしいイベント」を用意しておくと、気持ちの面でも満足感が得られやすくなります。
たとえば、提出後にふたりで外食をしたり、婚姻届のコピーを保存してフォトフレームに入れるといった工夫も良いでしょう。手続きを淡々とこなすだけでなく、ふたりにとって意味のある一日として演出することが大切です。
このように、心理的な側面にも配慮しながら進めることで、「ひとりでの提出」でも温かい記憶として残すことができます。
では次に、実際にひとりで婚姻届を提出した人たちのリアルな体験談を見ていきましょう。
実際にひとりで婚姻届を出した人の体験談

スムーズに終わった成功例
ひとりで婚姻届を提出することに不安を感じている人もいるかもしれませんが、実際には「拍子抜けするほど簡単だった」という声も少なくありません。
たとえば、東京都在住のAさん(30代女性)は、夫が繁忙期で休みが取れなかったため、ふたりで記入済みの婚姻届を持って、昼休みに自分だけで区役所へ行きました。
窓口では、本人確認と書類チェックが丁寧に行われたものの、全体でかかった時間は15分程度。持参した証人欄や戸籍謄本も完璧で、「何も問題なく終わった」と語っています。
さらに、記念に受理証明書も取得し、提出後にはふたりでレストランに行って入籍日を祝ったとのこと。彼女は「思ったよりもずっとスムーズで、手続きが終わってホッとした」と話していました。
このように、準備をしっかり整えていれば、ひとりでの提出もストレスなく終えることができるのです。
しかし一方で、予期せぬトラブルに見舞われた体験談も存在します。次に、そんなリアルな声をご紹介します。
トラブルがあったリアルな声
ひとりで婚姻届を提出した人の中には、思わぬトラブルに直面したという声もあります。その多くは、記入ミスや書類の不備に関するものです。
大阪府在住のBさん(20代男性)は、婚姻届を提出する前に「記入済みだから大丈夫」と思い込み、しっかり確認せずに役所に向かいました。しかし、窓口で「証人欄に住所の記入がない」と指摘され、再提出となってしまいました。
証人が遠方に住んでいたため、その場で訂正することができず、入籍予定日を過ぎてしまう結果に。Bさんは「書類は完璧だと思っていたのに、基本的なところでミスをしてしまった」と振り返ります。
また、別のCさん(40代女性)は、代理で婚姻届を提出した際に、夫の委任状を持参するのを忘れてしまいました。窓口では「代理提出は可能だが、本人の意思確認の書面が必要」と説明され、その日は受理されませんでした。
このように、些細なミスや見落としによって、スムーズにいかないケースもあるため、事前準備とダブルチェックが非常に重要です。
提出前には、必ず「ふたりで一緒にチェックする」「役所のホームページで必要書類を確認する」といった基本的な対策をしておくことで、トラブルを防ぐことができます。
では、実際にひとりで提出したことがパートナーとの関係性にどのような影響を与えたかを、次のセクションで見ていきましょう。
パートナーとの関係性に変化は?
ひとりで婚姻届を提出したことが、パートナーとの関係性にどのような影響を与えたのか――これは多くの読者が気になるポイントです。
体験者の声を集めると、「特に関係が悪化したり不仲になったりすることはなかった」という意見が大多数を占めています。むしろ、互いの信頼や協力関係をより強く感じたという前向きな声も多く見られます。
たとえば、福岡県在住のDさん(30代女性)は、「夫が多忙な中でも、婚姻届の記入や証人手配などを快く任せてくれたことがうれしかった」と語っています。ひとりで提出したことで「家庭の実務を自分が担う覚悟ができた」と前向きに捉えている様子でした。
一方で、「ちょっとした寂しさを感じた」「一緒に提出していたらもっと思い出になったかも」という感情を抱いた人も少なからずいます。
たとえば、提出後に「おめでとう」と伝えた際、パートナーが「もう提出したの?早いね」と少し拍子抜けしたような反応を見せたことで、「共有感が薄く感じた」と語ったケースもあります。
このようなすれ違いを避けるためには、提出後にLINEや電話などで「今、出してきたよ」と報告する、記念に一緒に写真を撮る、夕食を特別なものにするなど、小さな工夫で「ふたりのイベント」として再構築することが効果的です。
要するに、提出そのものが関係性に直接影響を与えるわけではなく、その前後でどれだけ思いやりや共有の工夫をできるかが鍵になります。
次は、婚姻届を出す前にふたりでしっかり話し合っておくべき重要なポイントを整理していきます。
婚姻届を出す前に話し合っておくべきこと

結婚の意思確認は十分に
婚姻届の提出は、法的な結婚の成立を意味する非常に重要な行為です。ひとりで提出する場合でも、ふたりの結婚に対する意思確認がしっかりと取れていることが大前提となります。
たとえば、日常会話の延長で「そろそろ出そうか」となんとなく合意したつもりになっていたが、片方はまだ正式な意思を持っていなかったというケースも、まれに起こり得ます。
このようなすれ違いを防ぐためには、「結婚することにお互い同意しているか」「婚姻届をいつ、誰が提出するか」「苗字の選択や本籍地の設定について共通認識があるか」といった点を明確にしておくことが重要です。
実際、過去には「片方が勝手に提出した」として婚姻届が受理された後に無効確認訴訟に発展した例もあるため、意思確認は慎重に行いましょう。
結婚は「ふたりの共同作業」です。提出がひとりであっても、その背景にはふたりの同意と準備があるべきなのです。
次に、提出のタイミングや記念日の共有についても、事前に話し合っておきたいポイントです。
提出日やタイミングの共有
婚姻届の提出日は、ふたりにとって「結婚記念日」として長く残る特別な日になります。そのため、誰がいつ提出するかについて、事前にしっかり共有しておくことが大切です。
とくにひとりで提出する場合、「提出する日をいつにするか」「パートナーがその日に納得しているか」「仕事や行事などと被らないか」など、提出前の調整が重要になります。
たとえば、「出会った日」や「付き合い始めた日」「どちらかの誕生日」など、ふたりにとって意味のある日を選んで提出することで、記念日としての価値が高まります。
一方で、提出日について何の相談もないまま、勝手にひとりで出してしまった場合、「自分にとって大事な瞬間を共有できなかった」と感じるパートナーもいます。
実際に、「妻が何の連絡もなく先に提出してしまい、少し残念だった。せめて相談があればよかった」と語る男性のケースもありました。
このようなすれ違いを避けるには、提出予定日を共有するだけでなく、その日にふたりで何か記念になることを行う計画も立てておくと良いでしょう。
たとえば、提出後に一緒に外食をする、プレゼントを交換する、記念写真を撮るなど、提出以外の部分で「ふたりの時間」を持つことで、片方が提出しても「ふたりで結婚した」という実感が生まれやすくなります。
このように、提出のタイミングに対する共有は、形式的なもの以上に、感情の行き違いを防ぐうえでも大切なステップなのです。
次は、婚姻届の提出に合わせて考えたい「思い出づくり」についてご紹介します。
記念写真や思い出作りの提案も
婚姻届の提出は、人生において特別な節目のひとつです。たとえひとりで提出する場合であっても、「ふたりの思い出」として形に残す工夫をすることで、より心に残る出来事になります。
たとえば、最近では「婚姻届提出フォト」が注目されており、役所の前で記念写真を撮るカップルが増えています。多くの自治体では、フォトスポットやフォトフレームを用意しており、誰でも気軽に記念写真を撮影できます。
ひとりで提出する場合でも、婚姻届を持った姿を自撮りしたり、役所のロビーでスマホのセルフタイマーを使ったりして、「提出の瞬間」を写真に収めることで、あとからパートナーと共有できます。
また、婚姻届のコピーをカラーで印刷し、記念フレームに入れて保管するというアイデアも人気です。中には、おしゃれな「記念用婚姻届」を販売している雑貨店もあり、ふたりの名前や結婚日をデザインできるテンプレートもあります。
他にも、提出当日に一緒にケーキを食べたり、手紙を交換したり、ミニアルバムを作成するなど、思い出の残し方はさまざまです。
たとえば、ひとりで提出したEさん(30代男性)は、提出後にパートナーのもとへ直行し、その場で「今日から夫婦だね」と言って小さな花束を渡したそうです。「サプライズだけど、ちゃんとふたりの時間になった」と微笑んでいました。
このように、たとえ提出をひとりで行ったとしても、ふたりの記念日として演出することは十分可能です。気持ちを込めた「思い出づくり」が、結婚のスタートをより幸せなものにしてくれます。
次は、婚姻届に関する「よくある質問」をQ&A形式でまとめてお答えします。
婚姻届に関するよくある質問【Q&A】

ひとりで出すと受理されないことはある?
- ひとりで提出しても、必要事項がすべて正確に記入されていれば受理されます。
- 提出時にふたり揃っている必要はありませんが、署名は必ず自筆で行う必要があります。
- 証人欄や本籍地の記入、戸籍謄本の添付などの条件が満たされていない場合は不受理となる可能性があります。
離婚届との違いとは?
- 婚姻届は「結婚の開始」を届け出るもので、離婚届は「結婚の終了」を知らせる書類です。
- 婚姻届には証人が2名必要ですが、協議離婚の場合の離婚届にも同様に証人が必要です。
- 婚姻届の受理日が「入籍日」になりますが、離婚届の受理日が「離婚日」となります。
- 婚姻届には氏の選択や本籍地の設定など、将来の生活に関わる記入項目が多くあります。
書き間違えたらどうする?
- 修正が必要な場合は、修正液や修正テープは使用せず、二重線を引いて訂正印を押しましょう。
- 大きなミスや何箇所も間違えてしまった場合には、新しい婚姻届に書き直す方が確実です。
- 婚姻届は役所で無料でもらえるため、複数枚用意しておくと安心です。
- 記入前に見本やガイドブックを参考にして、間違えやすい項目を事前にチェックしておくと良いでしょう。
まとめ
「婚姻届ひとりで出す割合」は年々増加しており、現代のライフスタイルや価値観を反映した自然な選択肢となっています。
共働きや遠距離恋愛、再婚や自由な意思決定など、背景は人それぞれですが、大切なのは「ふたりの合意と準備が整っていること」です。
ひとりでの提出はスケジュール調整が楽になり、実務的にも合理的です。ただし、書類の不備や証人の署名忘れなど、思わぬトラブルもあるため、事前の確認とダブルチェックが非常に重要です。
また、心理的な面でも「提出をふたりで共有したい」という気持ちがある場合には、記念日としての工夫や写真、プレゼントなどで補うことができるでしょう。
この記事では、統計データ、手続き方法、証人や委任状の詳細、メリット・デメリット、さらには実際の体験談までを紹介しました。
ひとりで婚姻届を出すという選択肢が「特別なこと」ではなく、「ふたりにとって最適なかたちのひとつ」として受け入れられる時代になった今、形式にとらわれず、ふたりらしい結婚のスタートを切っていただければと思います。
しっかり準備すれば、ひとりでの提出も安心して行えます。大切なのは、手続きを通じてお互いの絆を深めていくこと。それが本当の意味での“結婚”の始まりなのかもしれません。
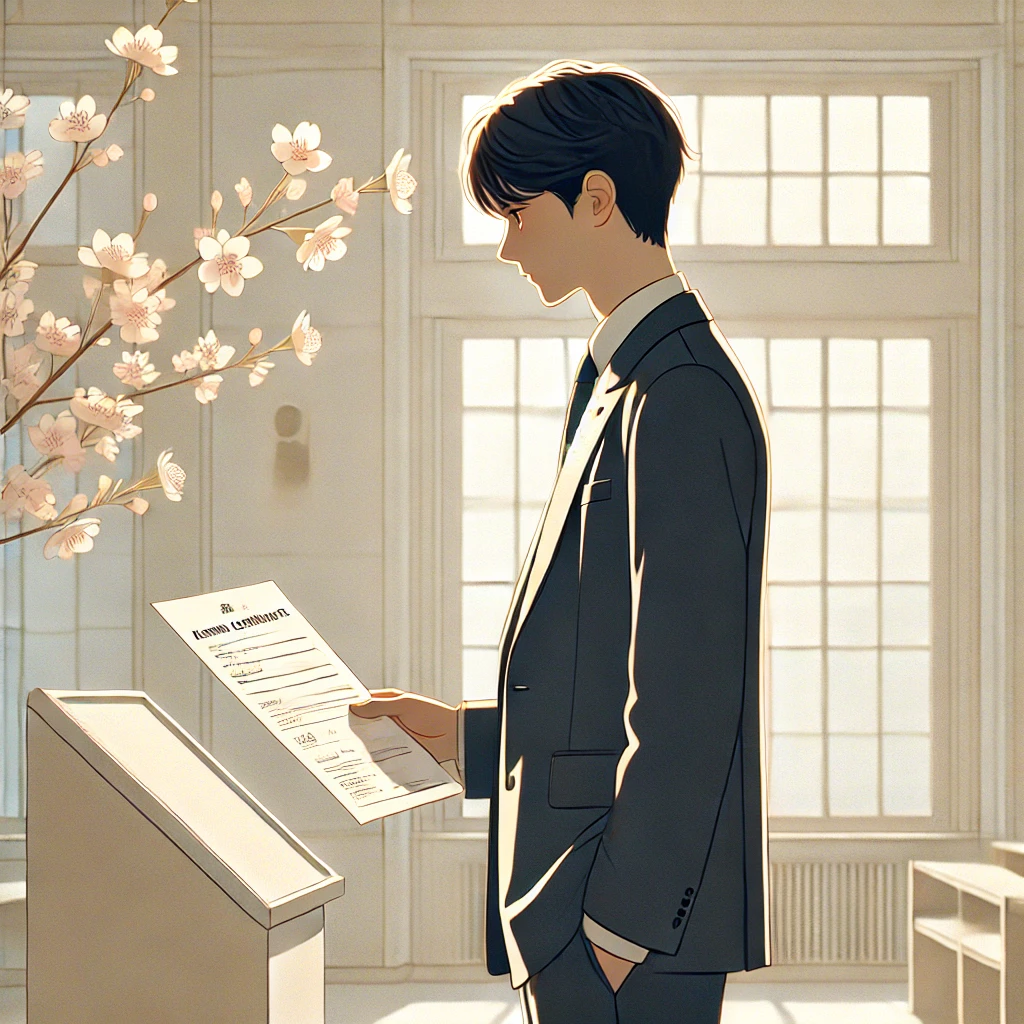


コメント