ドライアイスは冷却性能が非常に高いため、食品の保冷や演出効果などで広く利用されています。
しかし、その効果を最大限に活かすためには「ドライアイス 溶ける時間」について正しく理解しておく必要があります。
たとえば、アイスケーキを持ち帰るときや、イベントで長時間使用したいときなど、溶ける時間を知らなければ計画が狂ってしまうこともあります。
この記事では、保存状態や使用量によって変化するドライアイスの溶解時間や、冷蔵庫・冷凍庫での保存方法、安全な取り扱い方、さらには再利用のポイントまで詳しく解説します。
あらゆるシーンで活用できるよう、具体的な例や実験データも交えながら、わかりやすくお伝えしていきます。
それではまず、基本的な「ドライアイスが溶ける時間」の目安について見ていきましょう。
ドライアイスが溶ける時間はどれくらい?

室温で放置した場合の溶ける目安
室温(約20〜25℃)でドライアイスを放置すると、1kgあたりおよそ3〜5時間で完全に昇華してしまいます。
なぜなら、ドライアイスは水のように溶けて液体になるのではなく、固体の状態から直接気体に変わる「昇華」という現象を起こすためです。
たとえば、夏場にテーブルの上へ500gのドライアイスを置いておいたところ、2時間程度でほとんどの量が消えてしまったという実験報告もあります。
この昇華は、温度が高ければ高いほど加速します。
また、通気性のよい部屋や直射日光が当たる環境では、さらに溶ける時間が短縮される傾向があります。
つまり、室温での保存はドライアイスの保冷能力をすぐに失わせてしまうため、適した容器や保冷方法を用いる必要があります。
したがって、使用直前までの保存方法に気をつけることが重要です。
次に、より適した保存方法として「クーラーボックス」を使った場合の溶ける時間について見ていきましょう。
クーラーボックスで保存した場合
クーラーボックスを使うと、ドライアイスの溶ける速度は大きく抑えられます。
一般的な発泡スチロール製のクーラーボックスに入れた場合、1kgあたりおよそ18〜24時間ほど持つというデータがあります。
特に、クーラーボックスの内部を新聞紙で包む、あるいはタオルを被せて保冷効果を高めることで、さらに数時間延命できる可能性があります。
たとえば、釣りに出かけた際にクーラーボックスに1kgのドライアイスを入れて、日帰りの使用(約10時間)に十分耐えたという事例もあります。
また、クーラーボックスの構造や材質によっても保冷効果は異なります。
真空断熱構造の高機能ボックスを使えば、保冷力は格段にアップします。
このように、ドライアイスの保存には温度だけでなく、「どんな容器」を使うかが大きく影響してくるのです。
それでは、簡易的な容器である保冷袋や段ボールではどうなるのでしょうか。
保冷袋や段ボールでの変化
保冷袋や段ボールは、クーラーボックスに比べると断熱性能が劣るため、溶ける時間は短くなります。
目安としては、1kgのドライアイスで約6〜10時間程度です。
たとえば、アイスケーキの持ち帰りのために保冷袋に入れても、真夏の屋外では3時間程度でかなり昇華が進みます。
段ボールの場合も同様で、保温性はありますが、冷気が逃げやすいため、長時間の保存には向きません。
ただし、新聞紙を巻いたり、段ボールの中にタオルを敷き詰めて冷気の流出を防ぐ工夫をすると、ある程度の延命が可能です。
このように、簡易容器での保存には限界がありますが、短時間の移動や一時的な保冷には十分使えます。
ゆえに、使用目的に合わせて容器の選択が必要です。
ここまででドライアイスが「どのくらいで溶けるか」の基本的な時間目安がわかりました。
次に、使用量やサイズによってどのように溶け方が変わるかを見ていきましょう。
使用量やサイズで変わる溶解速度

小さいドライアイスはすぐに消える
ドライアイスはサイズが小さくなればなるほど、昇華するスピードが速まります。
というのも、表面積と体積の関係によって、小さなドライアイスは空気に触れる面積の割合が大きくなるため、より早く気化してしまうのです。
たとえば、同じ1kgのドライアイスでも、キューブ状に細かく分かれたものを使った場合、2〜3時間で消えてしまうのに対し、1kgの大きな塊にした場合は6時間以上持つというケースがあります。
実際、ケーキ屋で使われる小型のドライアイスは、受け取って30分もすると白い煙を出しながら一気に消えていきます。
これは温度や容器にもよりますが、サイズが小さいことで昇華が急速に進むことを示しています。
したがって、短時間での使用に向いているのが小型のドライアイスだと言えるでしょう。
では反対に、大きな塊のドライアイスはどのくらい持つのでしょうか。
大量の塊は長持ちする理由
大量のドライアイスや、ひとかたまりになった大きな塊は、表面積が少ないため昇華速度が遅くなります。
たとえば、業務用に使用される10kg以上のドライアイスを、専用のボックスで保存した場合、36〜48時間以上も持続することがあります。
実験では、10kgのドライアイスを発泡スチロール容器に入れ、新聞紙とタオルでくるんで保存した結果、約2日間で5kg程度が残っていたという報告もあります。
これはドライアイスの冷却力と共に、保存状態がいかに重要であるかを示しています。
また、大量のドライアイスを使うと冷気自体も内部に閉じ込めやすくなり、内部の温度が下がることで昇華速度もさらに遅くなるのです。
このように、大量にまとめて使えば時間的に余裕を持って使えるため、イベントや輸送など長時間の冷却が必要な場面に最適です。
では、具体的にどんな用途にどのくらいのドライアイスを使えば良いのかを見ていきましょう。
使用用途別の目安時間
ドライアイスの使用時間は、用途によって必要な量と保存時間が大きく変わります。
たとえば、アイスクリームやケーキの持ち運びには500g程度の小さなドライアイスで1〜2時間の保冷が可能です。
一方で、冷凍食品を6時間以上持たせたい場合は、2〜3kgのドライアイスが必要になるでしょう。
引越しやキャンプなどで冷凍品を1日以上保存するには、5kg以上の塊を専用ボックスで保存することが推奨されます。
たとえば、ある家庭では夏場にクーラーボックスと一緒に3kgのドライアイスを使い、朝から夜まで冷凍食品を無事に保冷できたという実例があります。
また、実験的にペットボトルに冷水とドライアイスを入れて、どのくらいの時間で全て昇華するかを測定したところ、500gでおよそ2.5時間という結果が出ました。
このように、使用用途ごとに適切な量を選ばなければ、冷却力が途中で失われるリスクがあります。
だからこそ、事前にどのくらいの時間保冷が必要かを明確にし、それに応じたドライアイスの準備が大切です。
ここで、なぜドライアイスが水にならずに「煙」になって消えていくのか、その仕組みについても理解しておきましょう。
溶ける過程で起きる「昇華」とは?

氷と違って水にならない理由
ドライアイスは溶けても水になりません。それは、「昇華」と呼ばれる特殊な現象が関係しています。
通常、氷は温度が上がると液体である水に変化しますが、ドライアイスは固体から直接気体になる性質を持っています。
つまり、ドライアイスは溶けるのではなく、蒸発するように消えていくのです。
この昇華は、ドライアイスの主成分である二酸化炭素の物理的性質に由来します。
たとえば、0℃の室温に氷を置けば時間とともに水たまりになりますが、同じ温度でドライアイスを置いても一滴の液体も残りません。
これは、水の融点が0℃であるのに対して、二酸化炭素は−78.5℃で昇華するため、通常の温度環境では常に気体になってしまうからです。
このような特性があるため、ドライアイスは液体を出さずに周囲を冷やすことができ、保冷用途には非常に便利です。
では、そのドライアイスが具体的にどんな物質なのか、もう少し詳しく見ていきましょう。
ドライアイスの正体=固体の二酸化炭素
ドライアイスの正体は、固体化された二酸化炭素です。
通常、二酸化炭素は空気中にごく微量含まれている気体ですが、これを−78.5℃以下の低温で急速に冷却し、圧力を加えることで固体にすることができます。
この冷却過程では特殊な装置が必要であり、主に産業用の冷却装置や液化ガスの処理施設で作られます。
たとえば、炭酸飲料に使われるガスと同じ成分を凍らせたものと考えると、イメージしやすいかもしれません。
また、ドライアイスは無色無臭で、自然界では通常の状態では存在しません。
さらに、昇華する際には熱を奪う(吸熱反応)ため、周囲の温度を大きく下げる性質があります。
だからこそ、食品や医薬品などの「低温保存」に非常に適しているのです。
では、ドライアイスから発生する白い煙のようなものは、一体何なのでしょうか。
昇華中に発生する「白い煙」の正体
ドライアイスが昇華するときに発生する白い煙のようなものは、実は二酸化炭素の気体ではありません。
その正体は、周囲の空気中にある水蒸気が冷やされてできた「細かい水の粒(霧)」です。
ドライアイスの表面温度は−78.5℃と非常に低いため、周囲の湿った空気が急冷され、目に見える水滴へと変わります。
たとえば、ドライアイスをコップの水に入れると、白いモクモクとした煙が水面から上がってきますが、これは気化したCO2が水中から抜け出しながら、空気中の水蒸気を冷やして霧状にしたものです。
この現象は化学実験の演出や、ハロウィンイベントなどでもよく使われています。
ちなみに、CO2自体は透明なので、煙のように見えるのはあくまで「水の粒」による視覚効果です。
このような昇華の特徴を理解しておくと、安全に、かつ効果的にドライアイスを使うことができます。
ところで、ドライアイスを家庭で保存する際、冷蔵庫や冷凍庫に入れても問題ないのでしょうか。
冷蔵庫や冷凍庫で保存できるの?

冷凍庫に入れるとどうなるか
ドライアイスを冷凍庫に入れて保存しようと考える方は多いですが、基本的に家庭用の冷凍庫での保存は推奨されていません。
なぜなら、ドライアイスの表面温度は−78.5℃と非常に低く、家庭用冷凍庫の内部温度(通常は−18℃程度)とは大きく差があるため、ドライアイスは冷凍庫内でも昇華してしまうからです。
たとえば、実験的に1kgのドライアイスを冷凍庫に入れたところ、6時間で半分以上が消えたというケースもあります。
しかも、昇華した二酸化炭素が冷凍庫の密閉空間に充満すると、庫内のセンサーやファンに影響を与える恐れもあります。
また、気化したガスが庫内の圧力や空気循環に干渉し、冷却性能を低下させる場合もあるのです。
したがって、冷凍庫はドライアイスの長期保存に適した環境とは言えません。
では、冷蔵庫での保存はどうでしょうか。
家庭用冷蔵庫での注意点
冷蔵庫もまた、ドライアイスの保存場所としては理想的ではありません。
その理由は、冷蔵庫内の温度が4〜8℃程度と高く、ドライアイスの昇華を止めるには不十分だからです。
たとえば、500gのドライアイスを冷蔵庫に入れた場合、1〜2時間でほぼすべて昇華してしまいます。
さらに、庫内に二酸化炭素が充満することで、内部の酸素濃度が低下する危険性もあります。
このガスが食品に直接触れたり、庫内の電子部品に結露を起こすなどのトラブルが発生することもあります。
なお、冷蔵庫や冷凍庫の密閉構造は、ドライアイスが気化しても逃げ場がないため、長時間放置すると内圧の上昇を招く可能性もあります。
このように、ドライアイスを家庭用の冷蔵庫で保存するのは、保冷効果も低く、機器にも悪影響を与えるリスクがあります。
それでは、どのような温度帯での保存が理想的なのでしょうか。
保存に向いている温度帯とは?
ドライアイスの保存に最適な温度帯は、外気の影響を受けにくく、かつ低温を保てる環境です。
具体的には、−50℃から−80℃の環境が理想ですが、これは家庭では実現が困難なため、現実的には「断熱性の高い容器」を使用し、外部との温度差を抑える工夫が重要です。
たとえば、専用の発泡スチロールボックスを使い、さらに新聞紙やタオルでくるむことで、内部温度を0℃近くまで下げ、昇華速度を大幅に抑えることができます。
また、気温が低い冬場はドライアイスの保存にも適しており、屋外の物置や車庫などを活用すると効果的です。
加えて、冷風が直接当たらない風通しの悪い場所を選ぶことで、気化を防ぎやすくなります。
たとえば、屋内で保存する場合でも、玄関近くや北向きの部屋のような比較的温度の安定した場所を使うと、ドライアイスの持ち時間が数時間延びることもあります。
したがって、保存温度だけでなく、「外気との接触をいかに遮断するか」がドライアイス保存の成功を左右します。
このような保存の基本を踏まえたうえで、次は実際にどのような方法がドライアイスの保存に適しているのかを紹介していきます。
ドライアイスの保存に適した方法

専用の発泡スチロールケース
ドライアイスの保存には、断熱性の高い「発泡スチロールケース」が非常に効果的です。
この容器は外部の温度変化を遮断し、内部の冷気を逃がしにくいため、ドライアイスの昇華速度を大幅に遅らせることができます。
たとえば、2kgのドライアイスを専用の発泡スチロールケースに入れ、蓋をしっかり閉めて保存した場合、気温25℃の室内でも12〜18時間ほど残量が確認されたという実験データがあります。
また、販売店でもドライアイスはこのようなケースに入れて保管されており、長時間の保存や輸送に欠かせないアイテムとなっています。
発泡スチロールは軽量で扱いやすく、持ち運びにも便利です。
ただし、完全密閉は避け、蓋は軽く乗せる程度にしておきましょう。なぜなら、気化した二酸化炭素が容器内に溜まると、内圧が高まり破損や爆発の危険があるからです。
したがって、安全に保存するためには、蓋に小さな通気口を設けるか、わずかに隙間を空けておくのがポイントです。
では、発泡スチロール以外にも身近なアイテムでドライアイスの保存時間を延ばす方法はあるのでしょうか。
新聞紙・タオルで包むと長持ち?
ドライアイスを新聞紙やタオルで包むことで、さらに昇華を抑える効果が得られます。
これらの素材は断熱性が高く、冷気を逃がしにくいため、ドライアイスを外気から守る「バリア」の役割を果たします。
たとえば、500gのドライアイスをそのまま段ボールに入れた場合は約4時間で消えてしまいますが、新聞紙で二重に巻いた上でタオルに包み、同じ段ボールに入れた場合には、6〜7時間程度持続したという報告があります。
また、保存の際にできるだけ隙間を埋めることも重要で、内部に空気の流れが生まれにくくなることで気化が抑制されます。
さらに、新聞紙やタオルは使い捨て可能で、衛生的にも管理しやすいため、家庭での簡易保冷には非常に便利です。
ただし、これらはあくまでも一時的な延命措置であり、長時間の保存には専用容器との併用が推奨されます。
それでは、保冷剤を使った場合にはどうなるのでしょうか。
保冷剤との併用でさらに延命
ドライアイスの保存効果をさらに高めたい場合は、保冷剤との併用が非常に有効です。
というのは、保冷剤はドライアイスほど温度は低くないものの、周囲の温度上昇を抑える役割を担うからです。
たとえば、発泡スチロールケースの底に保冷剤を敷き、その上に新聞紙とタオルで包んだドライアイスを置くと、ドライアイスが直接外気に触れるのを防ぎ、保存時間が2〜3時間延びるケースがあります。
また、保冷剤が蓄えた冷気によって容器内部の温度が安定し、ドライアイスの昇華がより緩やかになります。
この方法は、特に移動時間が長い旅行や配送時に役立ちます。
たとえば、引越しの際に冷凍食品を移動させるとき、保冷剤とドライアイスを併用したことで、8時間後も中身が完全に凍ったままだったという実例があります。
このように、工夫次第で家庭でもドライアイスを長持ちさせることは可能です。
ただし、保存方法以上に注意すべきなのが、ドライアイスの「取り扱い方」です。次に、使用時に気をつけるべき安全面について詳しく見ていきましょう。
ドライアイスの安全な取り扱い方

直接触れると危険な理由
ドライアイスは表面温度が−78.5℃と極端に低いため、素手で触れると凍傷を起こす危険があります。
この温度は皮膚の水分を一瞬で凍らせてしまうほどの冷たさで、数秒触れただけでも赤く腫れたり、感覚が麻痺したりすることがあります。
たとえば、実験的に手の甲で1秒間だけ500gのドライアイスに触れたところ、軽度の低温やけどが生じたという報告があります。
また、金属製のピンセットやトングで掴んだ場合でも、金属が急激に冷やされて皮膚に張り付くことがあるため、取扱いには注意が必要です。
安全に扱うためには、分厚い手袋(ゴム手袋よりも皮手袋が推奨されます)やトング、断熱シートなどを活用するのが基本です。
このように、ドライアイスは便利である反面、扱いを間違えると皮膚に深刻なダメージを与える可能性があるのです。
それでは、家庭内に子どもやペットがいる場合には、どのような注意が必要でしょうか。
子どもやペットがいる場合の注意
ドライアイスはその見た目や煙の演出効果から、子どもにとっては興味を引きやすい存在です。しかし、好奇心から素手で触れたり、口に入れてしまうなどの事故が発生する可能性があります。
たとえば、白い煙に興味を持った子どもが手を伸ばして触れてしまい、手のひらに軽度の凍傷を負ったという事例も報告されています。
ペットも同様で、床に置いておいたドライアイスを嗅ごうとした犬が、吸い込んだ二酸化炭素で一時的に苦しそうな呼吸をしたというケースもあります。
このような事故を防ぐには、ドライアイスを使用する際には子どもやペットの手の届かない高い場所に置く、または専用の容器に入れて管理することが必要です。
さらに、使用中は必ず大人が監視し、煙が出ている演出用の容器にも「触らないように」としっかり注意を促しましょう。
このような配慮を行うことで、家庭内での事故を防ぐことができます。
そして最後に、ドライアイスの大きなリスクとして「密閉空間での酸欠」があります。
密閉空間での酸欠リスク
ドライアイスが昇華すると、周囲に大量の二酸化炭素(CO2)が放出されます。
このガスは空気よりも重く、床や容器の底に溜まりやすいため、密閉された空間では酸素が押し出され、酸欠状態になる危険性があります。
たとえば、小さな車の中でドライアイスを使って冷凍食品を運んでいたところ、運転者がめまいや頭痛を訴え、窓を開けて二酸化炭素を排出したところ症状が改善したという実例があります。
また、冷蔵庫内や狭い倉庫で大量のドライアイスを保存していた場合、開けた瞬間にCO2が一気に噴き出し、呼吸困難を引き起こすこともあります。
したがって、使用する際は必ず換気を心がけ、密閉空間や狭い室内では使用を避けるか、短時間で済ませることが重要です。
特に、車中や押し入れのような通気のない場所では、絶対に放置しないようにしましょう。
このように、ドライアイスには冷却効果と引き換えに、いくつかの危険性が伴います。安全性を確保しながら使うには、取り扱いだけでなく処分方法にも注意が必要です。
再利用や捨て方に注意しよう

使い切れなかった場合の処理方法
ドライアイスは使い切れなかった場合でも、可燃ゴミや不燃ゴミとして捨ててはいけません。
その理由は、ドライアイスが気化する際に大量の二酸化炭素ガスを発生させるため、密閉されたゴミ袋や容器の中で内圧が上昇し、破裂する危険があるからです。
たとえば、家庭ごみの袋にドライアイスをそのまま入れて結んでしまったところ、袋が数分後に破裂し、中のゴミが飛び散ったという事故も実際に報告されています。
したがって、ドライアイスの正しい処分方法は「気体になるまで自然に昇華させる」ことです。
その際、風通しの良い屋外やベランダなどに置いておくのが理想です。
また、使用後すぐに処分できない場合は、新聞紙などに包んで発泡スチロール容器の中に入れておき、数時間後に安全に昇華させる準備をするとよいでしょう。
次に、より安全かつ早く気化させる方法について紹介します。
水に入れて気化させる方法
ドライアイスは水に入れると昇華速度が一気に加速します。
これは、水がドライアイスよりもはるかに高温であるため、熱が効率よく伝わり、短時間で気体へと変化するからです。
たとえば、ボウルに500mlの水を入れ、そこに100gのドライアイスを入れると、1〜2分程度で白い煙とともにすべて昇華してしまいます。
この方法は処分を急ぐ場合には効果的ですが、必ず以下の点に注意してください。
・屋外や換気のよい場所で行う
・小さな容器を使い、絶対に密閉しない
・子どもやペットの近くでは行わない
また、水の量が多いほど昇華が早くなるので、処理したいドライアイスの量に応じて調整するのがコツです。
ただし、後述の「NG行為」に該当する使い方は非常に危険ですので、必ず守りましょう。
絶対にやってはいけないNG行為
ドライアイスの処理や取り扱いにおいて、絶対にやってはいけない行為がいくつかあります。
まず一つ目は、「密閉容器に入れること」です。
たとえば、ペットボトルにドライアイスを入れて蓋を閉めた場合、短時間で内圧が上昇し、破裂事故に至る危険があります。
実際、子どもが実験のつもりでドライアイスを瓶に入れて蓋をしたところ、破裂してガラス片が飛び散り、大けがをしたという事例があります。
二つ目は、「トイレや排水口に流すこと」です。
急激な冷却により配管が破損したり、詰まりの原因になるため、絶対に避けてください。
三つ目は、「車内に放置すること」です。
密閉された車内では二酸化炭素濃度が高まり、酸欠や体調不良を引き起こす危険があります。
また、温度上昇によって一気に気化が進み、圧力のかかる危険性もあるため、ドライアイスは車内放置しないことが原則です。
このように、ドライアイスの処分には特有のリスクが伴うため、正しい知識を持って安全に対処することが重要です。
ここまでの内容を踏まえると、ドライアイスの使用には時間的な見積もりが極めて大切になります。
次に、実際のイベントや輸送時における持ち時間の目安について詳しく解説します。
イベントや輸送時の持ち時間目安
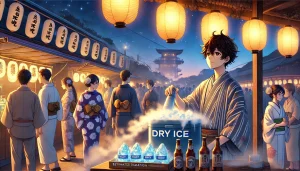
アイスケーキの持ち帰り時間
アイスケーキの持ち帰りには、ドライアイスがよく使われていますが、持ち時間の目安を把握していないと、到着時にケーキが溶けてしまうリスクがあります。
一般的に、店舗で提供されるドライアイスの量は300g〜500g程度で、保冷袋や紙箱に入れて持ち帰った場合、持続時間は約1〜2時間と考えるのが妥当です。
たとえば、30分以内に自宅へ到着する想定であれば問題ありませんが、真夏の昼間や1時間以上の移動がある場合は、追加でドライアイスを購入するか、クーラーボックスを使用するのが望ましいです。
また、保冷剤と併用すると冷却効果が高まり、持ち時間が30分〜1時間ほど延びることもあります。
このように、移動時間と環境温度に応じて、必要なドライアイスの量を調整することが重要です。
次は、冷凍食品を長時間保存する場合の持ち時間を確認してみましょう。
冷凍食品の保冷目安時間
冷凍食品の輸送には、ドライアイスが非常に有効です。しっかりとした容器に入れておけば、数時間から十数時間の保冷が可能です。
たとえば、2kgのドライアイスを発泡スチロールボックスに入れた状態で冷凍食品を保管した場合、外気温25℃前後でも8〜12時間の保冷が実現できます。
さらに、段ボールなどで容器を二重にしたり、保冷剤と一緒に使用することで、15時間以上の冷凍状態を維持するケースもあります。
実際に通販業者では、冷凍肉や海産物の配送に3〜5kgのドライアイスを使い、24時間以上の冷却を維持している例もあります。
このように、冷凍食品の保存には使用量と容器の工夫が保冷時間に直結します。
次に、引越しや長距離配送など、さらに時間がかかるケースでの対処法を紹介します。
配送や引越しで使う場合の工夫
引越しや長距離輸送で冷凍品を持ち運ぶ場合、ドライアイスの持ち時間をいかに延ばすかが大きな課題です。
このようなケースでは、以下のような工夫が効果的です:
・ドライアイスを大きな塊のまま使用する(昇華が遅くなる)
・発泡スチロール容器を使い、新聞紙・タオルで内部を覆う
・保冷剤を併用し、全体の温度上昇を防ぐ
・容器のフタに通気穴をあけ、ガスの逃げ道を確保する
たとえば、8時間かけて冷凍食品を他県に運ぶ場合、3kg以上のドライアイスと大型クーラーボックスを使ったことで、食品が完全に凍った状態で届いたという実績があります。
また、冷凍庫を積んだ移動車両でさえ、ドライアイスを併用することで急な停電や故障時の保冷対策としても活用されています。
このように、輸送やイベントでのドライアイスの使用には、時間と環境に応じた柔軟な対応が必要です。
次は、読者の疑問に答える形式で、よくある質問とその回答を紹介していきます。
よくある質問(FAQ)

-
- 溶けたドライアイスの煙を吸っても大丈夫?
ドライアイスの煙の正体は、気化した二酸化炭素と冷却された水蒸気による霧です。少量であれば大きな害はありませんが、密閉空間で多量に吸い込むと酸欠の原因になるため注意が必要です。特に換気の悪い場所では使用を控えましょう。
- 溶けたドライアイスの煙を吸っても大丈夫?
-
- 冷却力は氷よりも強いの?
はい、ドライアイスの冷却力は通常の氷よりもはるかに高いです。氷の温度が0℃なのに対し、ドライアイスは−78.5℃と極端に低温であるため、冷却スピードが非常に速く、長時間の保冷にも適しています。
- 冷却力は氷よりも強いの?
-
- どこで買えて、どれくらい保存できるの?
ドライアイスはスーパー、ケーキ店、冷凍食品専門店、またはガス販売業者などで購入できます。保存可能時間は保存環境によって大きく異なりますが、専用の発泡スチロールボックスなどで保存すれば、2kgで12〜24時間程度が目安です。
- どこで買えて、どれくらい保存できるの?
以上のような疑問点を把握しておくことで、より安心してドライアイスを活用することができます。



コメント