小学校の通知表に記載する「保護者からの一言」は、子どもの頑張りを認め、先生への感謝を伝える大切な役割を持っています。
しかしながら、いざコメント欄に向き合うと、どんな言葉を選んで良いのか悩む保護者は少なくありません。
そこで今回は「保護者からの一言 小学校」というテーマで、基本から具体例、学年別の例文、成績に応じた書き方、避けたい表現までを網羅的に解説します。
この記事を読むことで、学校と家庭の良好なコミュニケーションを築くためのコメント作成法をしっかり学べます。
さらに、先生に喜ばれるポイントや他の保護者の工夫も紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。
通知表の保護者コメントとは?基本を押さえよう

通知表には、学校から子どもへの評価だけでなく、保護者から学校への気持ちを伝える欄があります。
つまり、保護者コメント欄は単なる感想ではなく、先生と家庭の橋渡し役となる大切な役割を果たしているのです。
保護者コメント欄の目的
保護者コメント欄の最大の目的は、子どもの学校での様子を踏まえて、家庭での成長や学びを先生に伝えることです。
たとえば、通知表に「算数の理解が深まった」と書かれていれば、家庭ではどのように勉強を頑張ったかを添えると良いでしょう。
このように、先生への感謝を含めつつ、指導への協力姿勢を伝えることで、より良い学校生活をサポートできます。
そして、子ども自身の自信にもつながるので、前向きな言葉選びが大切です。
いつ誰が書くのか
通知表のコメント欄は、ほとんどの場合、保護者が学期末などに書くことが一般的です。
しかし、学校によっては保護者面談の際に先生と直接話し合い、口頭で伝えることもあります。
また、共働き家庭では、父母のどちらが書いても問題ありませんが、可能であれば子どもの勉強の様子をよく把握している方が担当するとスムーズです。
ちなみに、私の家庭では、宿題を一緒に見る機会が多い母親が書くことが多いです。
ただし、学校の指示に合わせて柔軟に対応しましょう。
どのくらいの文量が適切?
では、実際にどれくらいの長さを書けば良いのでしょうか。
一般的には2~3行程度、100文字から200文字以内が読みやすく適切とされています。
たとえば、「算数の問題に自信を持てるようになった様子が家庭でも見られました。今後も先生のご指導のもと、さらなる成長を期待しています。」といったシンプルかつ具体的なコメントが好まれます。
だらだらと長文になると、読み手である先生に負担をかけてしまう可能性があるため注意が必要です。
したがって、要点を絞りつつ、子どもの良い面と感謝を簡潔に伝えましょう。
次に、コメントを書く際の具体的なポイントとマナーについて詳しく解説していきます。
コメントを書く際のポイントとマナー

通知表の保護者コメント欄を書くときは、子どもの頑張りを正しく伝えるだけでなく、学校との信頼関係を深める機会でもあります。
ここでは、具体的なポイントやマナーを押さえておくことで、先生に伝わりやすく、かつ保護者としての思いをしっかり届ける方法を紹介します。
丁寧で前向きな言葉選び
まず、何よりも大切なのは、丁寧な表現と前向きな言葉を選ぶことです。
たとえば、「算数が苦手でしたが、先生のおかげで少しずつ自信を持てるようになりました」といった具合に、苦手な点を補ってくれた指導への感謝を含めると良いでしょう。
逆に、「まだまだ勉強が足りません」とだけ書くと、先生に対して厳しい印象を与えてしまいます。
私の場合、子供が算数を克服した際、「自宅でも計算問題を自主的に取り組む様子が増え、家庭でも成長を感じています」と付け加えたところ、先生から「努力が伝わって嬉しい」と言われたことがあります。
したがって、前向きな言葉選びを心がけましょう。
子どもの成長を具体的に書く
続いて、子どもの成長をできるだけ具体的に表現することがポイントです。
「頑張っています」という一言よりも、「漢字テストで満点を取るために、毎日5分だけ復習する習慣がつきました」と書く方が、先生にも様子が伝わりやすくなります。
また、通知表に書かれている内容とリンクさせると、より一貫性があり、先生も家庭での取り組みを把握しやすくなります。
このように、勉強面だけでなく、友達との関わり方や学校での出来事なども織り交ぜると、バランスの良いコメントになります。
感謝の気持ちを添える
最後に欠かせないのが、先生への感謝の気持ちです。
普段、面と向かって伝えにくい感謝を、コメント欄で素直に表すことで、先生も保護者の気持ちを感じ取れます。
たとえば、「先生の温かいご指導のおかげで、家でも宿題に前向きに取り組むようになりました」と書くだけでも印象が良くなります。
学校と家庭が協力し合う姿勢を示すと、子どもにとっても安心感につながります。
以上のポイントを押さえることで、自然で読みやすく、心のこもったコメントを作成できます。
では次に、学年別にどのような例文が適しているかを紹介していきます。
学年別コメント例文集【低学年】

低学年の通知表コメントでは、子どもが学校生活に慣れ、基本的な生活習慣や学習習慣が身についてきた点を中心に書くと良いでしょう。
低学年の子どもはまだ自己管理が不十分なため、学校での様子を踏まえた成長の具体例を挙げて、先生に家庭での取り組みも伝えましょう。
1年生のコメント例
1年生では、入学して初めての学校生活への適応を認める言葉を中心にすると安心感があります。
たとえば、「初めは緊張していましたが、先生やお友達のおかげで楽しく学校に通えるようになりました。家庭でも毎日『今日の学校どうだった?』と話を聞いています。」といった形です。
このように、学校での様子と家庭での関わりを繋げると、先生も安心して指導ができます。
2年生のコメント例
2年生になると、少しずつ学習内容が増えてくるため、勉強への取り組みを具体的に褒めると良いでしょう。
例文としては、「算数の計算練習を家でも頑張っています。わからないところは自分から質問できるようになり、成長を感じています。先生の丁寧なご指導に感謝しています。」などが適切です。
特に、先生の教え方に対する感謝を忘れないことが大切です。
低学年で意識するポイント
低学年では、無理に難しい表現を使わず、素直な言葉で子どもの日常を伝えるのがポイントです。
また、長文にせず、「学校が楽しい」「先生が優しい」といった安心感を込めることで、学校と家庭が一体となって子どもを支えていることが伝わります。
ちなみに、1年生の頃は些細なことでも褒めると子どもの自信につながるので、家庭での小さな変化も書いてみてください。
次は、中学年のコメント例について詳しく見ていきましょう。
学年別コメント例文集【中学年】

中学年になると、学習内容も増え、友人関係やクラス活動など学校生活がより充実してきます。
そのため、通知表コメントでは勉強面だけでなく、友達との関わりや家庭でのサポートの様子も具体的に伝えると良いでしょう。
3年生のコメント例
3年生では、学年が上がり自立心が芽生える時期です。
たとえば、「算数の文章問題に苦戦していましたが、先生の丁寧な指導のおかげで、家でも自分から問題集に取り組むようになりました。友達とも仲良く過ごしている様子を家でも楽しそうに話してくれます。」といった内容が好ましいです。
このように、学校と家庭の連携が感じられる一文がポイントです。
4年生のコメント例
4年生は学習の難易度が一段階上がり、クラスでの役割も増えてくる学年です。
「社会科の調べ学習に意欲的に取り組み、わからないことは家族にも積極的に質問してきます。先生のアドバイスを参考に、家庭でも図鑑やインターネットで調べる習慣がついてきました。」など、具体的な学習の取り組みを書きましょう。
先生への指導に対する感謝を添えることで、学校と家庭の協力体制が伝わります。
中学年で意識するポイント
中学年では、勉強への意欲とともに、友達との関係やクラスでの協調性も成長の大きな指標です。
そのため、「友達と一緒に課題に取り組む姿勢が見られます」など、人間関係にも触れると良いコメントになります。
また、子供が自分の意見を発表できるようになったり、行事で役割を果たした話も具体例として適しています。
ちなみに、子どもの苦手分野については無理に詳細を書かず、「引き続き家庭でも見守っていきます」と前向きに締めくくるのがポイントです。
それでは、次に高学年のコメント例を紹介していきます。
学年別コメント例文集【高学年】

高学年になると、学習内容が一段と難しくなり、責任感やリーダーシップが育つ時期です。
そのため、通知表コメントでも、子どもが主体的に考え、行動できるようになった点を具体的に伝えると良いでしょう。
5年生のコメント例
5年生では、委員会活動やクラブ活動など、学校内での役割が増えるため、それらを含めて書くと先生に伝わりやすくなります。
例文としては、「学級委員としてクラスの意見をまとめる役割を楽しんでいます。家庭でも学校での出来事をよく話してくれ、責任感が育っていると感じています。これからも先生のご指導をよろしくお願いします。」などが適切です。
このように、学校での成長を家庭でも感じていることを具体的に述べましょう。
6年生のコメント例
6年生は小学校生活のまとめの学年です。
中学校への進学を見据えたコメントにすると、先生にとっても安心感があります。
たとえば、「最高学年として下級生の面倒を見たり、学校行事でリーダーを務める様子を誇らしく感じています。中学校でもこの経験を活かしてくれることを期待しています。」といった内容が適切です。
先生の指導と家庭の支えが子どもの成長を支えていることを感じさせる一文にしましょう。
高学年で意識するポイント
高学年では、子ども自身の自立心を大切にすることがポイントです。
勉強面だけでなく、学級活動や地域活動への参加など、主体性を評価する言葉を加えると良い印象を与えられます。
また、進学を控えているため、「中学校でも自信を持って頑張れるよう、家庭でも支えていきます」と締めくくると自然です。
ちなみに、私の家庭では卒業前に先生への感謝の気持ちを少し多めに伝えるようにしています。
次は、成績別にどのようにコメントを使い分ければ良いのかを見ていきましょう。
成績別の書き分け例と注意点

通知表の保護者コメントは、子どもの成績に合わせて内容を工夫することで、先生に伝わりやすくなります。
ここでは、良い成績、普通の成績、やや心配な場合の例を紹介しながら、注意点を解説します。
良い成績の場合
成績が良い場合でも、単に「すごいです」と褒めるだけでなく、先生の指導のおかげであることを強調しましょう。
たとえば、「算数のテストで満点が増え、自信を持って勉強に取り組む様子が見られます。先生のわかりやすいご指導のおかげだと感謝しています。」といった内容が適しています。
また、今後の目標を添えると、子どもの更なる成長を応援する姿勢が伝わります。
普通の成績の場合
普通の成績の場合は、できることに焦点を当てつつ、努力を認めて前向きに書くことが大切です。
例文として、「宿題を忘れずに取り組む姿勢が身につきました。これからも先生のご指導のもと、苦手な部分を一緒に克服していきたいと思います。」などが良いでしょう。
子供の小さな努力を評価し、家庭でも支える意志を示すと印象が良くなります。
やや心配な場合の例
やや心配な場合は、否定的な言い方は避け、これからの取り組みに触れると良いでしょう。
たとえば、「算数の文章題でつまずくことが多いようですが、家庭でも一緒に復習し、少しずつ理解が深まってきました。引き続き先生のご指導をお願いいたします。」といった形です。
このように、子どもの成長を信じ、家庭での支援を伝えることで、先生も安心して指導できます。
なお、成績に関わらず、比較や叱責を書くのは避けましょう。
次に、避けたい表現やNG例について詳しくお伝えします。
NG例と避けたい表現

通知表の保護者コメントを書く際には、つい使いがちな言い回しでも、先生に誤解を与えたり、子どもを傷つけてしまうことがあります。
ここでは、避けたい表現例と、その理由を説明します。
否定的すぎる表現例
「全然できていない」「全く成長していない」といった強い否定は避けましょう。
たとえば、「勉強が全然できないので心配です」と書くより、「苦手な部分もありますが、家庭でも少しずつ取り組んでいきたいです」と前向きに言い換えるのが良いです。
このようにすることで、先生も励ましやすくなります。
余計なアドバイスは控える
通知表コメント欄は、先生に指導方法を提案する場所ではありません。
たとえば、「もっと厳しく指導してください」「テストを増やしてください」といった要望は、先生の指導方針を否定しているように受け取られることもあります。
要望がある場合は、個別面談などの機会に相談しましょう。
子どもの気持ちを考える
保護者コメントは、子どもが読む可能性があることも念頭に置きましょう。
厳しい言葉やプレッシャーを感じる表現は避け、「頑張っている姿をこれからも見守ります」といった応援する言葉を意識してください。
ちなみに、私の知り合いの家庭では、否定的なコメントを避けてから、子どもの学習意欲がぐんと上がったという話もあります。
したがって、子どもの自己肯定感を高める言葉選びを心がけましょう。
次は、先生が思わず笑顔になる、印象の良いコメントのコツを紹介します。
先生が喜ぶ!印象の良いコメントのコツ

通知表の保護者コメントは、先生との信頼関係を築く大切な手段です。
ここでは、先生が読んで嬉しくなる褒め言葉や、努力を認める一言、家庭の協力姿勢を上手に伝えるコツを紹介します。
先生が嬉しい褒め言葉
先生が喜ぶのは、子どもの成長に対して「先生のおかげです」と素直に伝える言葉です。
たとえば、「算数が苦手だった子どもが、最近は自信を持って取り組むようになりました。先生のわかりやすいご指導のおかげです。」と具体的に書きましょう。
こうした言葉は、先生の指導の励みになります。
努力を認める一言
子どもの努力を認める一言も忘れずに。
「漢字テストに向けて、家でも一緒に練習する姿が見られます。おかげで少しずつ自信がついてきました。」のように、家庭での様子を絡めると自然です。
努力を認めると、子どもにも伝わり、自信がつきます。
家庭の協力姿勢を伝える
最後に大切なのが、家庭が学校と一緒に子どもを支えている姿勢を示すことです。
「引き続き、家庭でも苦手分野を一緒に学び、先生のご指導を支えていきたいと思います。」などの一言で、先生に安心感を与えられます。
ちなみに、こうした協力姿勢を伝えると、先生とのコミュニケーションが円滑になりやすいです。
次は、保護者からよく寄せられる質問とその解決法についてお伝えします。
よくある質問とお悩み解決

最後に、通知表の保護者コメントについて、よくある質問とその解決方法をQ&A形式で紹介します。
-
- どのくらいの長さが適切?
2〜3行程度、100〜200文字が目安です。短くても構いませんが、子どもの様子と感謝の気持ちを含めると伝わりやすいです。
- どのくらいの長さが適切?
-
- 書く時間がないときは?
無理に長文を書かず、「毎日元気に学校へ通えていることを嬉しく思います。先生のご指導に感謝しております。」といった短文で十分です。
- 書く時間がないときは?
-
- 他の保護者はどうしてる?
多くの保護者は、子どもの学校での様子を一言伝え、先生への感謝を簡潔にまとめています。具体例を1つ入れるだけで自然なコメントになります。
- 他の保護者はどうしてる?
まとめ
小学校の通知表に書く「保護者からの一言」は、子どもの頑張りを認め、先生に家庭での様子を伝える大切な役割を担っています。
この記事で紹介したポイントを意識すれば、誰でも自然で温かみのあるコメントを書くことができます。
学校と家庭が協力して、子どもがより安心して学校生活を送れるよう、これからも思いやりのある言葉でつながりを深めていきましょう。
ちなみに、忙しいときは無理せず短文でも大丈夫です。大切なのは、先生と子どもに「見守っています」という気持ちが伝わることです。
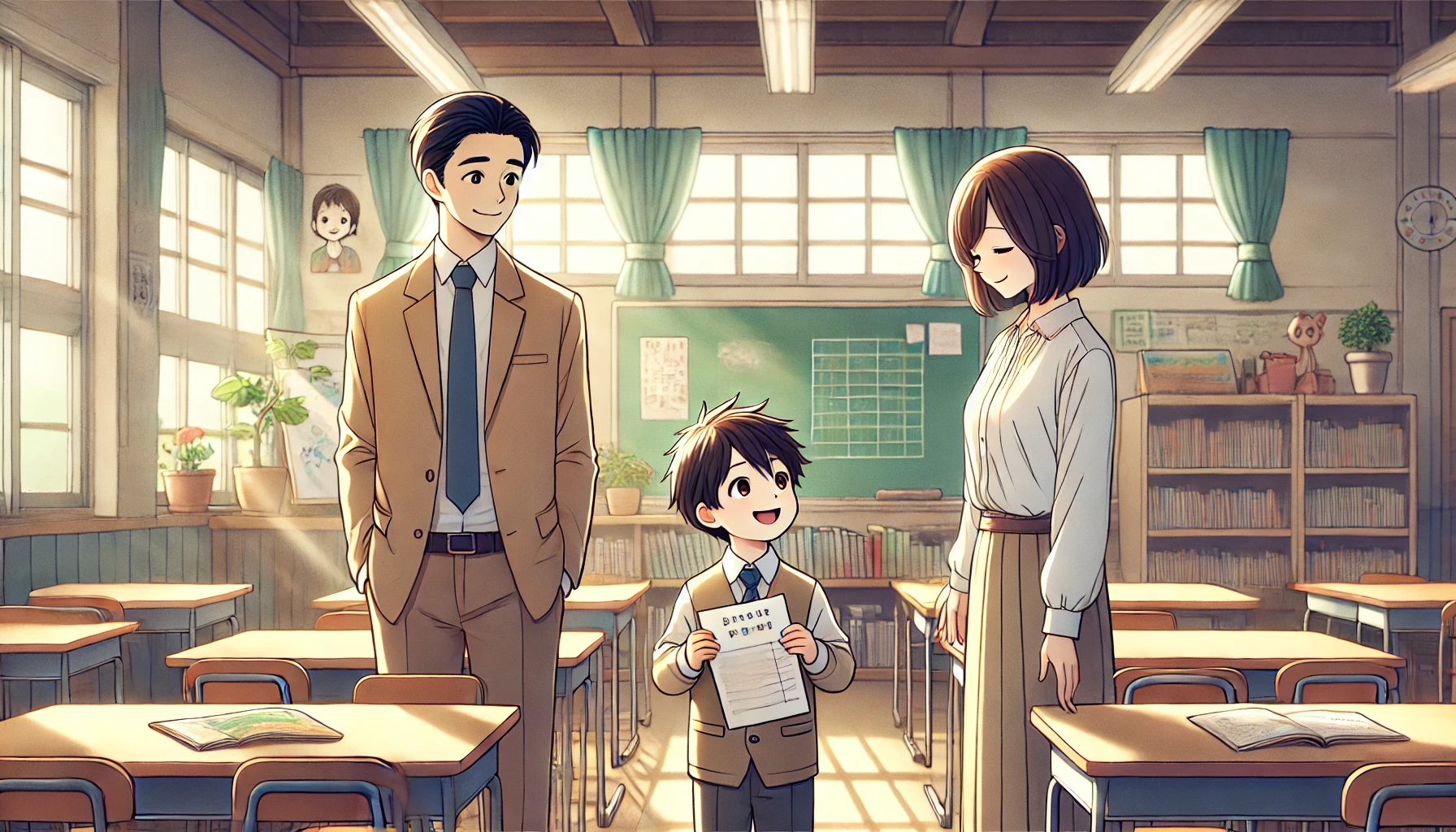


コメント